目次
「支柱の設置方法やポイントを知りたい」
こんな疑問や悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。電気柵に使用する支柱は、電気が流れる柵線を支える役割を担っています。しかしいざ商品を購入するとなると、どんな素材があるのか、どんな基準で選べばいいのか迷ってしまうものです。
そこで今回は電気柵の支柱の選び方をご紹介します。支柱の設置方法やポイントについても解説していますので、設置前の参考材料にしてください。
電気柵の支柱の選び方は?

電気柵の支柱を選ぶ際は、3つのポイントを確認して商品を選んでみましょう。
1.素材から選ぶ
1つ目のポイントは素材です。支柱に使用される素材は、「FRP」と「樹脂被膜」の2種類が一般的です。
FRP
【メリット】- 軽くて反発力に優れている
- 電気を通さない
またプラスチックを原料としているため、電気を通さないのもFRPの特徴。支柱が金属製の場合、柵線が少しでも触れると支柱部分にまで電気が流れてしまいます。これでは電気柵の効果が下がってしまいますが、FRPなら電気を通さないため、効果が下がる心配がありません。
金属製と違い錆びる心配がないのもメリットです。
★FRP素材のおすすめ商品はこちら
樹脂皮膜
【メリット】- 丈夫で強度が高い
- 重量があるのでしっかり刺さる
イノシシやクマといった大型の動物が近づくと支柱が折れ曲がる場合がありますが、樹脂皮膜タイプなら強度が高いため耐久性にも優れています。
金属製なので使用時はガイシ(碍子)を使って、柵線と支柱が接触しないよう注意して設置してください。
★樹脂皮膜素材のおすすめ商品はこちら
2.支柱の高さから選ぶ
2つ目は支柱の高さです。電気柵は動物の種類によって柵線の段数を調整しますが、支柱の高さ(商品の長さ)も対象動物に合わせて調節します。たとえばシカのような大柄な動物は支柱の高さが低いと、上部の柵線を飛び越えて田畑に侵入する恐れがあります。
支柱を選ぶ際は、どの動物を対象として電気柵を設置するのかあらかじめ想定し、最適な高さの商品を選んでみましょう。
【支柱の高さの目安】
- イノシシ:90cm~
- 小動物:90cm~
- シカ:250cm~
- サル:250cm~
- クマ:250cm~
3.ガイシ付きや足踏み式から選ぶ
3つ目は支柱の機能です。支柱には柵線を支えるためのガイシが一体型になったタイプや、地面の埋め込み作業がはかどる足踏み式のタイプも販売されています。電気柵の設置作業は重労働なだけに、こうした機能が付いた商品を選んで作業の手間を軽減するのもおすすめです。

★ガイシ付き支柱のおすすめ商品はこちら

★足踏み式支柱のおすすめ商品はこちら
ガイシを増やして柵線の段数を調整する
ガイシは、支柱と柵線が触れないようにするための絶縁器具です。電気柵では各支柱にガイシを取り付け、柵線の段数を調整します。段数を調整したい場合は、ガイシを新たに購入してみましょう。またガイシは経年劣化により割れや曲がりが発生します。消耗品と考えて、定期的に交換を検討してください。
ガイシは柵線が弛まないようにする目的でも用います。一箇所だけ柵線が垂れ下がるように設置されているだけでも、野生動物にとっては格好の侵入経路です。電気柵の効果を十二分に発揮するためにも、ガイシの破損や抜けがないか定期的にチェックしておきましょう。

★おすすめのガイシ商品はこちら
支柱の設置方法4つのポイント
電気柵の効果を発揮するには、適切に支柱を設置する必要があります。ここでは、支柱の設置方法のポイントを4つご紹介します。ポイント1.下草や周囲の枝を刈り取る
支柱を設置する際は、まず設置する地面の下草や周囲の枝を刈り取っておきましょう。柵線が雑草や枝に触れてしまうと、漏電が発生してしまい電気柵の効果が弱まってしまいます。周囲にコンクリートや石がある場合も漏電の原因となります。支柱とコンクリートとは最低でも50cm以上の距離を保つようにしてください。また地面はできるだけならしておき、支柱が安定して設置できるよう整えておきます。
ポイント2.対象の動物に合わせて間隔を調整する
支柱を設置するときは、対象の動物に合わせて支柱同士の間隔を調整しましょう。種類によって最適な間隔が違ってくるので、下記の表を参考に調整してください。また支柱を設置する際は、ハンマー等を使ってしっかりと地面に突き刺します。刺し方が不十分だと、動物が接触した衝撃や台風等の強風で支柱が倒れてしまいます。地面と垂直になるように確認しながら、支柱を設置していきましょう。
|
動物 |
支柱の間隔 |
|
イノシシ |
2~4m |
|
シカ |
3~4m |
|
サル |
3~4m |
|
クマ |
4m以内 |
|
タヌキ・ハクビシン |
4m以下 |
ポイント3.設置場所の凹凸や状態に応じて柵線や支柱を増やす

設置場所に凹凸があると、柵線の間隔が広くなってしまい動物の侵入経路ができてしまいます。こうした場所では柵線や支柱の数を増やすなどして、侵入経路を塞ぐようにしましょう。
うまく支柱と柵線を組み合わせて、田畑への侵入経路を塞げば電気柵の効果がさらに高まります。
ポイント4.傾斜地からは距離を離して設置する

支柱を設置する場所は、傾斜地から距離を取るようにしましょう。 傾斜地に近い位置に支柱があると、傾斜の角度を利用して動物が電気柵を飛び越えてしまいます。傾斜から距離が離れていれば、電気柵の効果をしっかり確保できます。 どうしても傾斜に支柱を設置する必要がある場合は、その箇所だけ高い支柱を設置するなどして侵入しづらいよう対策を講じましょう。
まとめ
今回は電気柵に使用する支柱の選び方や設置方法についてご紹介しました。支柱は柵線を支えるだけでなく、柵線同士をつなぎ、野生動物の侵入経路を塞ぐ重要な役割をはたします。動物の種類や設置場所に応じて高さ(商品の長さ)も豊富に揃っているため、状況に応じて最適な商品を選んでみましょう。
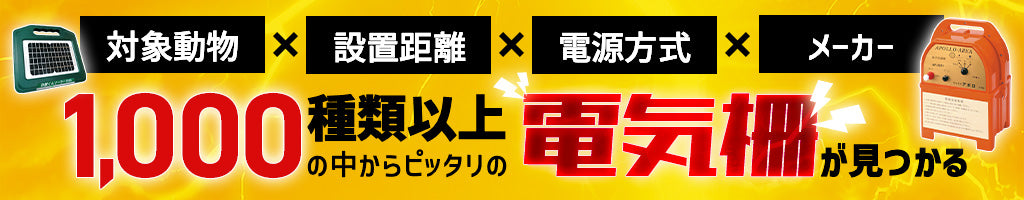

 箱罠
箱罠
 くくり罠
くくり罠
 パーツ類
パーツ類
 電気柵
電気柵
 自作キット
自作キット
 防獣グッズ
防獣グッズ
 監視カメラ
監視カメラ












 box trap
box trap
 tying trap
tying trap
 enclosure trap
enclosure trap
 Prevention and avoidance goods
Prevention and avoidance goods
 electric fence
electric fence
 trap surveillance camera
trap surveillance camera
 transportation goods
transportation goods
 Trap detection sensor
Trap detection sensor
 hunting supplies
hunting supplies
 hunting books
hunting books
 Anti-bird goods
Anti-bird goods
 Agricultural materials/machinery
Agricultural materials/machinery
 boar
boar
 deer
deer
 Kyon
Kyon
 monkey
monkey
 raccoon
raccoon
 Badger
Badger
 palm civet
palm civet
 raccoon dog
raccoon dog
 nutria
nutria
 mouse or rat
mouse or rat
 Mole
Mole
 bear
bear
 pigeon
pigeon
 Crow
Crow







