32GB SDHC card for trail cameras
32GB SDHC card for trail cameras

商品説明
◯ An SD card for saving image/video data taken with the trail camera .
・ SanDisk class 10
・Super high speed 90MB/s (read), 40MB/s (write)
・U3 compatible
・4K compatible
・Size: 24mm x 32mm x 2.1mm

 箱罠
箱罠
 くくり罠
くくり罠
 パーツ類
パーツ類
 電気柵
電気柵
 自作キット
自作キット
 防獣グッズ
防獣グッズ
 監視カメラ
監視カメラ




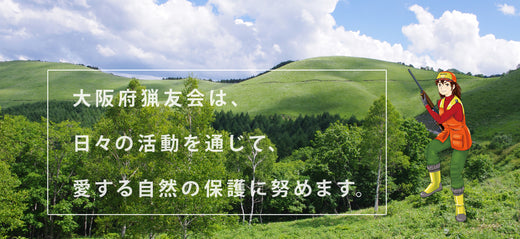

 box trap
box trap
 tying trap
tying trap
 enclosure trap
enclosure trap
 Prevention and avoidance goods
Prevention and avoidance goods
 electric fence
electric fence
 trap surveillance camera
trap surveillance camera
 transportation goods
transportation goods
 Trap detection sensor
Trap detection sensor
 hunting supplies
hunting supplies
 hunting books
hunting books
 Anti-bird goods
Anti-bird goods
 Agricultural materials/machinery
Agricultural materials/machinery
 boar
boar
 deer
deer
 Kyon
Kyon
 monkey
monkey
 raccoon
raccoon
 Badger
Badger
 palm civet
palm civet
 raccoon dog
raccoon dog
 nutria
nutria
 mouse or rat
mouse or rat
 Mole
Mole
 bear
bear
 pigeon
pigeon
 Crow
Crow







